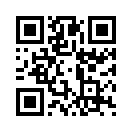› しゅんさんブログ › 辺野古環境影響評価書提出について。2
› しゅんさんブログ › 辺野古環境影響評価書提出について。22011年12月19日
辺野古環境影響評価書提出について。2
政府は、12月26日に、環境影響評価書を県に提出する方向で調整をすすめているとの報道がなされています。
方法書、準備書は、欠陥だらけで、到底、環境アセスの体をなしていません。
意見書 第二部 を掲載します。
方法書に関する部分までです。
第2 環境影響調査方法書作成前の環境現況調査(事前調査)の違 法性について。
1 方法書作成手続に先立ち、2007年5月18日から「環境 現況調査」を強行した。
2 環境影響評価法上の「環境影響評価のための調査」に相当す るものである以上、環境影響評価法が定める環境影響評価手続 を経て実施されなければならない。
これは、住民等意見や知事意見の提出の機会が奪われ、環境 影響評価法の採用する民主的統制制度や地域的特性を環境影響 評価に反映させるという環境影響評価法の本旨を完全に無視す るものである。
3 新石垣空港アセス訴訟那覇地裁判決(2009年2月24 日)は、沖縄県が方法書作成手続に先立って調査を行った点に ついて、「事業者である沖縄県は、環境影響評価法が予定して いる本来の手続(まず方法書を作成して、これに対する意見を 勘案・配意して環境影響評価を行い、準備書を作成する)を行 っていたのでは長期間を要するとして、(主務省令に基づく) 「現地の状況確認のための調査」の方法を利用して、本来同 省令が予定する同目的に必要な範囲の調査に止まらず、その範 囲を超え、方法書の作成に先立って「環境影響評価としての調 査」を行おうとしたものといえる。」と事実認定した上で、 「このような沖縄県の態度は、環境影響評価を行うに先立つ手 続として方法書の手続を定めた法の趣旨を没却しかねないもの というべきである。」と指摘した。
同判決は、「方法書作成手続に先立つ環境影響評価として の調査は、法の趣旨を没却しかねないものである。」と指摘し ている。
本件において、沖縄防衛局は、環境現況調査の位置づけに ついて、「本来ならば、環境影響評価法に則った手続で粛々と 進めたいが、まだ、沖縄県あるいは名護市との間で現在の政府 案の形状はともかく、位置については十分合意に達していない ところでございます。しかしながら、2014年までに代替施 設を完成させるという目的で、私どもはできる範囲で、私ども の所掌事務の範囲の中で移設先周辺の環境にかかる様々なデー タを収集することが、今後の作業を円滑順調に進める上で必要 なことと認識しております。」などと説明していた(2007 年5月21日の那覇防衛施設局<当時>佐藤勉局長の説明)。
まさに、先に挙げた那覇地裁判決が判示するとおり、環境影 響評価法の趣旨を没却する違法な調査である。
4 調査事項は膨大であり、到底「現地の状況確認のための調査」の限度に止まらない。ジュゴン調査手法について、約30億円ともいわれる巨費を投じ、①30箇所にパッシブ ソナー(設置機器数:30)、②海草藻場に食餌にくるジュゴンを把握するとして、14箇所に水中ビデオカメラ(設置機器数:14)、③サンゴ類調査のためとして39箇所にサンゴの幼群体着床具(設置機器数:39)(本件方法書作成後の環境影響調査では43箇所、設置機器数:43)、④海象調査機器29個所(設置機器数:82)(同環境影響調査では49個所、設置機器数:129)⑤全体で112箇所(設置機器数:165)(同環境影響調査では136個所、設置機器数:216)に調査機器を設置したというものであって、到底「計画を立案するための調査」「現地の状況確認のための調査」とはいえず、明らかに、環境影響評価法に反する行為であると言わざるを得ない。
とりわけ、ジュゴン調査に関して、沖縄防衛局は、その生息 調査手法について、これを一切明らかにしないまま実施した。
その調査経過は、ジュゴンの生息「環境」に重大な影響を与 えながら、ジュゴン「調査」が行われたと言っても過言ではな い。
また、忘れてはならないのは、那覇防衛施設局は、2007 年5月18日から、海上自衛隊・掃海艇「ぶんご」を投入し、 海上保安庁所属の多数の大小船舶を配置した上で、環境現況調 査を強行した。その後も、海上保安庁所属の多数船舶が、それ も、これら多数船舶のうちの大型ゴムボート(複数)は、米軍 基地(キャンプ・シュワブ)から出入りしながら、継続的に配 置され、所謂事前調査が行われた。
このような状況は、本件方法書に基づく環境影響調査でも継 続的に維持されている。
このような船舶の配置も、ジュゴンに影響を与えるものであ って、ジュゴンの生息環境の改変(ジュゴンの締め出し)、す なわち、ジュゴンの生息環境の破壊そのものといえる。
5 違法な事前調査により、環境破壊を実行した上で行われた、 環影響調査は、到底有意性をもたず、違法な調査等によって破 壊された環境が修復された後、再度、法令にしたがって環境影 響評価手続がとられるべきであって、相当期間の修復期間をお いて後、法令に従って、方法書作成手続の段階からやり直すべ きである。
ボーリング調査用足場設置工事が、本格的に開始された20 04年9月9日頃から、すでに、ジュゴンが締め出されたと考 えられるが、それ以前においては、キャンプシュワブ側の海岸 近くをも含む辺野古沖においてジュゴンの食跡がしばしば確認 されている。
第3 環境影響評価方法書と、追加・修正資料、追加・修正資料(修正版)の提出の評価について
・・・環境影響評価法5条 方法書作成義務違反
1 手続経過について。 経過は、前記経過表の通りであ るが、
① 2007年8月14日に環境影響評価方法書の公告縦覧が 行 われ
これに対して住民意見等がなされ、
沖縄防衛局(当時那覇防)は、
② 2007年10月22日に、住民等意見をまとめた「方法 書に関する意見の概要」を、沖縄県に交付している。
③ 審査会からの
事業者が実施している環境現況調査は、ジュゴンやサンゴ類等の 生物的環境への影響が懸念されることから、これらの調査の実施によ る環境への影響を十分に検討させた上で調査の中止も含め検討させ る必要があると考える。との意見をうけて、
④ 2008.01.11 資料追加提出
⑤ 2008.02.05 「方法書に対する追加・修正資料」を提出
⑥ 2008.03.14 方法書に対する追加・修正資料(修正版)を提出◎
している。
⑦ ⑥の修正版を提出した翌日の2008年3月15日には、 環境影響評価方法書に基づく、環境影響調査に着手している。
2 時系列的に整理すると、沖縄防衛局による環境影響評価方法 書作成手続は、単に、住民等の意見陳述権を侵害しているに止 まらず、環境影響評価法上権限を有する沖縄県環境影響審査会 の権限すら否定する極めて不当な手続であることが明らかであ る。
3 住民等の意見は、2007年8月14日に公告縦覧すること のできた、わずか7ページの事業計画案の方法書に対してしか、 意見を述べる機会は与えられていない。
従って、前記意見のみが「意見の概要」としてまとめられて、 いる。
4 追加・修正資料、追加・修正資料(修正版)を提出しなけれ ば、そもそも、審査会の審査の対象にもなり得ないということ であり、そもそも、2007年8月14日に公告縦覧された環 境影響評価方法書が、方法書の体をなしていないことをしめす ものであり、そもそもが、環境影響評価法第5条に定める方法 書作成義務の不履行であり、作成義務違反である。
5 環境影響評価法5条は、方法書に記載すべき内容について、
法定しており、
1 事業者の氏名及び住所
2 事業の目的内容
3 事業対象が実施されるべき区域
4 対象事業にかかる環境影響評価の項目並びに調査、予 測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあ っては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
を記載することを求めている。
詳細は、主務省令で定める (公有水面の埋め立て又は、 干拓の事業にかかる環境影響評価の項目並びに当該項目に係 る調査、予測及び評価を合理的におこなうための手法を選定 するための指針環境の保全のための措置にかんする指針等を 定める省令。(平成10,農、運、建令一)による。
一方、県条例の対象となる空港建設については、「沖縄県 環境影響評価技術指針」が定められており、
1 対象事業の種類。
2 対象事業実施区域
3 対象事業の規模及び内容に関する事項
4 対象事業にかかる工事計画
5 対象事業計画の背景、検討経緯及び必要性
6 その他、対象事業の内容に関する事項(既に決定されて いる内容に係るものに限る)であって、その変更により環 境影響をうける範囲であると認められる地域
なお、前記5は、平成19年11月1日施行の変更県条例 に基づき加入修正された事項であるが、改正前にも、「対 象事業計画の検討経緯」が記載事項となっており、これを具 体化したにすぎず、 検討経緯の内容として、上記5の事項 の記載が必要であると考える。
6 当初提出され、公告縦覧された方法書は、アセス方法の案 であって、これに対して、住民等意見を述べ、更に市町村長 の意見を聞いて、県知事が意見を提出して、その後、アセス の方法が決定されることになる。
環境影響評価方法書は、その後行われる基本であり、アセ スの方法の決定のための基本となるべき程度の詳細性、具体 性がなければならない。
単に記載要件を形式的に記載し、主要な事項は、事後に出 せばいいというのであれば、環境影響評価法の手続そのもの を脱法することになる。
7 そもそも本件では、単に住民意見を述べる機会を奪った後 に追加資料を提出したというだけではなく、審議会どころか、 知事意見が出た後に、提出されたものである。
環境影響評価方法書の内容として記載すべき事項を、異常 な「後出しに」よって提出し、知事意見の対象にすらならず、 沖縄県文化環境部長という、環境影響評価法上も、県条例上も、何ら の権限を持たないものの意見がだされたのみである。
8 これは、当初方法書の変更があったといえるものではなく、 そもそも、事業者に求められる方法書作成義務の不履行であ り、法の要求する方法書作成義務違反であるというべきであ る。
アセス手続は、方法書をアセス調査のいわば、設計図とし て、出発点とするものである。手続の基本が違法であり存在 しないものであれば、これを基本として、その後に行われる 手続は、当然に違法となるというべきである。
9 本件方法書には記載がなく、追加・修正資料によってはじ めて明らかにした事実は次の通りである。
① 約1700万立方メートルの埋立土砂を沖縄県内外から調達すること(追加・修正資料41~42頁)
② 米軍がジェット機(C-35)を配置すること(同2頁)
③ 米軍航空機が集落上空を飛行することもあり得ること(同6頁)
④ 920mと430mの進入灯を設置すること(同3頁)
⑤ 洗機場を3か所設置すること(同4頁)
追加・修正資料の提出をせざるを得なかったのは、結局、公告・縦覧に供され、住民等の意見の対象となった本件方法書が環境影響評価方法書の体をなしておらず、環境影響評価方法書として必要な事項の記載が欠落していることを示すものである。
10 なお、県条例の方法書記載要件からいうと、前述のとお り、「対象事業計画の背景、検討経緯及び必要性」(改正前 は、「対象事業計画の検討経緯」)の記載が必要であるが、 その記載は追加・修正資料や準備書にも含まれていない。
a 沖縄県民の総意を無視しても、本件事業が必要であるとの 説明を、怠っているのである。
1997年12月21日には、「名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票」が実施され、投票の総数の54%余りが基地建設に反対の意思表示をした。
基地建設に反対する住民意思は明らかであって、これを尊重するのが、民主主義の基本である。
1996年7月16日、沖縄県議会は、「普天間飛行場の全面返還を促進し、基地機能強化につながる県内移設に反対する決議」を、全会一致で決議した。
本件基地建設の地元、名護、沖縄県のいずれも、本件基地建設に反対しているのであり、地方自治、住民意思を否定してでも本件基地建設を必要とする、事業の目的、及び内容を明示しなければならない。
本件方法書には、県民の総意に反しても実行すべき必要性を根拠づける、事業の目的及び内容を明示しなければならないが、事業の必要性に関する説明は、何らなされていない。
b 本事業予定地を選択した理由について、環境面からの説明 を怠っていること。
辺野古崎沿岸海域が、生物多様性豊かな地域であり、絶滅の危険性が最も高い絶滅危惧類等が生息する。
本件方法書には、このような生物多様性豊かな辺野古崎及びその沿岸海域に、なに故に、本事業が計画されたのか、環境面からの説明が、一切ないのである。
11 後出しされた、2度にわたる追加・修正資料の提出は、 環境影響評価法の定める手続を脱法するものである。
本来、環境影響評価方法書に記載すべき事項であって、 容易に記載しうる事項である。
環境影響評価法は、調査予測評価の手法が決定されてい ないとき場合には、対象事業に係る環境影響評価の項目を 記載するように求めているが、本件方法書で記載されなか った事項は、明らかに、批判を回避するための「意図的な 必要な記載要件の逸脱」といわざるを得ない。
そもそも、本来方法書に記載すべき事項を意図的に逸脱 し、環境影響評価法に定める手続(住民等意見、市町村意 見、県知事意見)のいずれの検討評価も受けることなく、
重要な事項に関して、追加変更した修正資料を提出したと しても、これは、本来、環境影響評価法の予定する手続と は異なり、脱法行為というべきであるから、事後に提出さ れた事項をもって、アセスの方法の決定があったとは言え ないのである。 追加修正事項は、環境影響評価方法書の 内容にはなり得ないというべきである。
12 端的に言えば、追加・修正資料、追加・修正資料(修正 版)は、環境影響評価法第5条の求める、方法書作成義務 に反する行為であり、前記の通りの手続を開始している事 情からしても、瑕疵を修補正する効果は生じない。
従って、本件環境影響評価方法書は、そもそも、作成義 務を尽くしておらず、違法であるというべきである。
13 いわばアセスの設計図である方法書が違法であるので あるから、その後の環境影響調査も方法書に基づかない、 違法な調査であり、その成果としても準備書も、いずれも 違法であり、それ以上に、極めて違法性が高いというべき である。
第4 環境影響評価方法書と、追加・修正資料、追加・修正資料 (修正版)の提出に対して、意見陳述の機会が与えられなかっ たこととその評価について
1 意見陳述権をどのように評価するかの問題である。
環境影響評価法第8条、第18条は、方法書及び準備書に対し、意見を 述べることを認めている。
これは、環境権ないしは環境に直接間接にかかわる住民の権利ないしは 利益を保護するために、法が手続的な権利ないしは法的保護に値する利益 を認め、これを保障するものというべきである。
良好な環境の保全は、持続可能な社会のために不可欠であ り人間生存の基礎であることから基本的人権であるといいう ると同時に、個人の主観的権利の保護だけでは保全しえない ものである。
その中から、環境保全の仕組みが構築され、国による環境 保護義務や、公共信託論が議論されている。
我が国の環境基本法の理念には、環境権や環境保護義務な どについての明確な法規や公共信託理論の立法化もなされて ないが、環境基本法3条は、環境の保全が「現在及び将来の 世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するととも に人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持される ように適切に行わなければならない」と規定している。これ は、国や個人の責務を認めたものということができ、基本法 の一つたる環境基本法のかような定めは、環境影響評価法 解釈においても、十分尊重されなければならない。
2 日本の環境法制は、世界的レベルに至っていない点もおおい。
ところで、オーフス条約は、環境問題に関する
(1)情報へのアクセス権、
(2)意思決定における市民参画、
(3)司法アクセス権についての国際的な最低基準
を定めたものである。
環境環法を解釈するには、世界的レベルを反映させながら
解釈すべきである。環境保護の世界性からしても、当然であ る。
3 すなわち、環境保護と、その享受を得るため、
ア 情報へのアクセス
イ 政策決定への参加
ウ 司法へのアクセス
を求めているのである。
4 わが国はオーフス条約に未加盟であるが、これをヨーロッ パ独自の法制度と無視するのは不当である。国際的な環境保 全のための法思想の展開、地球サミットのリオ宣言などを経 て、オーフス条約が今日の環境法の一つの到達点となっている ことを、わが国においても十分認識し、その思想を反映させて いく必要があるといわねばならない。
5 環境影響評価法における意見陳述の意義
① 環境影響評価手続の本質
さて、環境影響評価手続を、事業者に任せたままではどこまで環境配慮がされるかはわからないため、環境影響が大きいと予想される行為の選択については、これを社会的に管理することが必要となる。
アセスメントは環境を配慮した意思決定のための、社会的な手続きである。
環境問題は、選択を誤れば深刻かつ広範な被害をもたらすことになるが、その被害は第一次的に直接被害を受けると予想される者のみならず、環境の相互依存性から、全地球的な市民の利害に直接関わる事象である。
これに対して、事業実施主体が自ら環境配慮を行うだけでは、不十分な結果を招きかねず、そのために利害関係のある全市民に関与させて社会的決定をなそうとするのが環境影響評価手続の本質ということができる。
② 環境影響評価法の定め
ア わが国の環境影響評価法における環境影響評価手続は、 事業者が各段階の手順を進める度に住民と地方自治体にそ の成果を明らかにし、それらの意見を踏まえて環境影響評 価の内容を修正し、さらに必要に応じて前段階の手続まで 立ち戻って手続をやり直すことによって、適切な環境影響 評価がなされるべく予定している。
すなわち、事業者は、方法書作成後には、住民意見(同法8条 以下引用法律同じ)と都道府県知事等の意見(10条)を受け、前者の意見に「配意し」、後者の意見を「勘案」して方法書の事項に検討を加え、「対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。」(11条1項)。そして、環境影響評価を実施(12条)した後に作成する準備書についても、住民意見(18条)と都道府県知事等の意見(20条)を受け、準備書を修正して評価書を作成することになる(21条)。
その結果、「対象事業の目的及び内容」に修正を加える場合には原則として方法書作成からやり直しを求められる(21条1項1号 5条1項2号)。また、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法、環境影響評価の結果や環境保全措置等に修正がある場合にはその部分についてさらに環境影響評価を行わなければならない(21条1項3号)。
また、方法書の公告後に対象事業の目的及び内容に修正が生じた場合には、修正後の事業について改めて環境影響評価手続を行わなければならず(28条)、評価書の公告後の情況の変化等により環境影響評価の変更の必要が生じた場合にはそれについて環境影響評価を行う手続も規定されている(32条)。
このように、環境影響評価手続においては、環境影響評価の項目や手法の選定、その実施の結果に対する評価等について、対象事業の目的と内容を明らかにして関連づけ、住民や都道府県知事等の意見を幾層もの段階で反映させることによって、その適正が担保される仕組みになっている。
イ 環境影響評価法が、方法書、準備書及び評価書の多数の段階における公告縦覧を求め、住民や地方自治体等からの意見を求める仕組みとされているのは、前述のとおり、今日における環境保全が、単に事業者の自主的な努力のみによってはなされえず、地域住民の参加を経て社会的合意を図ることによってなされるべきであるという発想に立っていることからである。
③ 環境影響評価における市民参加
環境の保全は、環境破壊によって一次的直接的に権利を侵害 される当事者のみならず、全市民、そして将来世代にわたっ ての持続可能な発展のために不可欠のものと認識されてきて おいる。
環境影響評価手続における市民参加は、全市民に対し、環 境保全のための権利を付与し責務を課すことによって、実効 性を図ろうとするものである。
したがって、環境影響評価法の制定によって、同法に定めた住民参加の上記諸規定は、住民に対して、それら手続的権利の保障を明らかにしたものということができるのである。


方法書、準備書は、欠陥だらけで、到底、環境アセスの体をなしていません。
意見書 第二部 を掲載します。
方法書に関する部分までです。
第2 環境影響調査方法書作成前の環境現況調査(事前調査)の違 法性について。
1 方法書作成手続に先立ち、2007年5月18日から「環境 現況調査」を強行した。
2 環境影響評価法上の「環境影響評価のための調査」に相当す るものである以上、環境影響評価法が定める環境影響評価手続 を経て実施されなければならない。
これは、住民等意見や知事意見の提出の機会が奪われ、環境 影響評価法の採用する民主的統制制度や地域的特性を環境影響 評価に反映させるという環境影響評価法の本旨を完全に無視す るものである。
3 新石垣空港アセス訴訟那覇地裁判決(2009年2月24 日)は、沖縄県が方法書作成手続に先立って調査を行った点に ついて、「事業者である沖縄県は、環境影響評価法が予定して いる本来の手続(まず方法書を作成して、これに対する意見を 勘案・配意して環境影響評価を行い、準備書を作成する)を行 っていたのでは長期間を要するとして、(主務省令に基づく) 「現地の状況確認のための調査」の方法を利用して、本来同 省令が予定する同目的に必要な範囲の調査に止まらず、その範 囲を超え、方法書の作成に先立って「環境影響評価としての調 査」を行おうとしたものといえる。」と事実認定した上で、 「このような沖縄県の態度は、環境影響評価を行うに先立つ手 続として方法書の手続を定めた法の趣旨を没却しかねないもの というべきである。」と指摘した。
同判決は、「方法書作成手続に先立つ環境影響評価として の調査は、法の趣旨を没却しかねないものである。」と指摘し ている。
本件において、沖縄防衛局は、環境現況調査の位置づけに ついて、「本来ならば、環境影響評価法に則った手続で粛々と 進めたいが、まだ、沖縄県あるいは名護市との間で現在の政府 案の形状はともかく、位置については十分合意に達していない ところでございます。しかしながら、2014年までに代替施 設を完成させるという目的で、私どもはできる範囲で、私ども の所掌事務の範囲の中で移設先周辺の環境にかかる様々なデー タを収集することが、今後の作業を円滑順調に進める上で必要 なことと認識しております。」などと説明していた(2007 年5月21日の那覇防衛施設局<当時>佐藤勉局長の説明)。
まさに、先に挙げた那覇地裁判決が判示するとおり、環境影 響評価法の趣旨を没却する違法な調査である。
4 調査事項は膨大であり、到底「現地の状況確認のための調査」の限度に止まらない。ジュゴン調査手法について、約30億円ともいわれる巨費を投じ、①30箇所にパッシブ ソナー(設置機器数:30)、②海草藻場に食餌にくるジュゴンを把握するとして、14箇所に水中ビデオカメラ(設置機器数:14)、③サンゴ類調査のためとして39箇所にサンゴの幼群体着床具(設置機器数:39)(本件方法書作成後の環境影響調査では43箇所、設置機器数:43)、④海象調査機器29個所(設置機器数:82)(同環境影響調査では49個所、設置機器数:129)⑤全体で112箇所(設置機器数:165)(同環境影響調査では136個所、設置機器数:216)に調査機器を設置したというものであって、到底「計画を立案するための調査」「現地の状況確認のための調査」とはいえず、明らかに、環境影響評価法に反する行為であると言わざるを得ない。
とりわけ、ジュゴン調査に関して、沖縄防衛局は、その生息 調査手法について、これを一切明らかにしないまま実施した。
その調査経過は、ジュゴンの生息「環境」に重大な影響を与 えながら、ジュゴン「調査」が行われたと言っても過言ではな い。
また、忘れてはならないのは、那覇防衛施設局は、2007 年5月18日から、海上自衛隊・掃海艇「ぶんご」を投入し、 海上保安庁所属の多数の大小船舶を配置した上で、環境現況調 査を強行した。その後も、海上保安庁所属の多数船舶が、それ も、これら多数船舶のうちの大型ゴムボート(複数)は、米軍 基地(キャンプ・シュワブ)から出入りしながら、継続的に配 置され、所謂事前調査が行われた。
このような状況は、本件方法書に基づく環境影響調査でも継 続的に維持されている。
このような船舶の配置も、ジュゴンに影響を与えるものであ って、ジュゴンの生息環境の改変(ジュゴンの締め出し)、す なわち、ジュゴンの生息環境の破壊そのものといえる。
5 違法な事前調査により、環境破壊を実行した上で行われた、 環影響調査は、到底有意性をもたず、違法な調査等によって破 壊された環境が修復された後、再度、法令にしたがって環境影 響評価手続がとられるべきであって、相当期間の修復期間をお いて後、法令に従って、方法書作成手続の段階からやり直すべ きである。
ボーリング調査用足場設置工事が、本格的に開始された20 04年9月9日頃から、すでに、ジュゴンが締め出されたと考 えられるが、それ以前においては、キャンプシュワブ側の海岸 近くをも含む辺野古沖においてジュゴンの食跡がしばしば確認 されている。
第3 環境影響評価方法書と、追加・修正資料、追加・修正資料(修正版)の提出の評価について
・・・環境影響評価法5条 方法書作成義務違反
1 手続経過について。 経過は、前記経過表の通りであ るが、
① 2007年8月14日に環境影響評価方法書の公告縦覧が 行 われ
これに対して住民意見等がなされ、
沖縄防衛局(当時那覇防)は、
② 2007年10月22日に、住民等意見をまとめた「方法 書に関する意見の概要」を、沖縄県に交付している。
③ 審査会からの
事業者が実施している環境現況調査は、ジュゴンやサンゴ類等の 生物的環境への影響が懸念されることから、これらの調査の実施によ る環境への影響を十分に検討させた上で調査の中止も含め検討させ る必要があると考える。との意見をうけて、
④ 2008.01.11 資料追加提出
⑤ 2008.02.05 「方法書に対する追加・修正資料」を提出
⑥ 2008.03.14 方法書に対する追加・修正資料(修正版)を提出◎
している。
⑦ ⑥の修正版を提出した翌日の2008年3月15日には、 環境影響評価方法書に基づく、環境影響調査に着手している。
2 時系列的に整理すると、沖縄防衛局による環境影響評価方法 書作成手続は、単に、住民等の意見陳述権を侵害しているに止 まらず、環境影響評価法上権限を有する沖縄県環境影響審査会 の権限すら否定する極めて不当な手続であることが明らかであ る。
3 住民等の意見は、2007年8月14日に公告縦覧すること のできた、わずか7ページの事業計画案の方法書に対してしか、 意見を述べる機会は与えられていない。
従って、前記意見のみが「意見の概要」としてまとめられて、 いる。
4 追加・修正資料、追加・修正資料(修正版)を提出しなけれ ば、そもそも、審査会の審査の対象にもなり得ないということ であり、そもそも、2007年8月14日に公告縦覧された環 境影響評価方法書が、方法書の体をなしていないことをしめす ものであり、そもそもが、環境影響評価法第5条に定める方法 書作成義務の不履行であり、作成義務違反である。
5 環境影響評価法5条は、方法書に記載すべき内容について、
法定しており、
1 事業者の氏名及び住所
2 事業の目的内容
3 事業対象が実施されるべき区域
4 対象事業にかかる環境影響評価の項目並びに調査、予 測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあ っては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
を記載することを求めている。
詳細は、主務省令で定める (公有水面の埋め立て又は、 干拓の事業にかかる環境影響評価の項目並びに当該項目に係 る調査、予測及び評価を合理的におこなうための手法を選定 するための指針環境の保全のための措置にかんする指針等を 定める省令。(平成10,農、運、建令一)による。
一方、県条例の対象となる空港建設については、「沖縄県 環境影響評価技術指針」が定められており、
1 対象事業の種類。
2 対象事業実施区域
3 対象事業の規模及び内容に関する事項
4 対象事業にかかる工事計画
5 対象事業計画の背景、検討経緯及び必要性
6 その他、対象事業の内容に関する事項(既に決定されて いる内容に係るものに限る)であって、その変更により環 境影響をうける範囲であると認められる地域
なお、前記5は、平成19年11月1日施行の変更県条例 に基づき加入修正された事項であるが、改正前にも、「対 象事業計画の検討経緯」が記載事項となっており、これを具 体化したにすぎず、 検討経緯の内容として、上記5の事項 の記載が必要であると考える。
6 当初提出され、公告縦覧された方法書は、アセス方法の案 であって、これに対して、住民等意見を述べ、更に市町村長 の意見を聞いて、県知事が意見を提出して、その後、アセス の方法が決定されることになる。
環境影響評価方法書は、その後行われる基本であり、アセ スの方法の決定のための基本となるべき程度の詳細性、具体 性がなければならない。
単に記載要件を形式的に記載し、主要な事項は、事後に出 せばいいというのであれば、環境影響評価法の手続そのもの を脱法することになる。
7 そもそも本件では、単に住民意見を述べる機会を奪った後 に追加資料を提出したというだけではなく、審議会どころか、 知事意見が出た後に、提出されたものである。
環境影響評価方法書の内容として記載すべき事項を、異常 な「後出しに」よって提出し、知事意見の対象にすらならず、 沖縄県文化環境部長という、環境影響評価法上も、県条例上も、何ら の権限を持たないものの意見がだされたのみである。
8 これは、当初方法書の変更があったといえるものではなく、 そもそも、事業者に求められる方法書作成義務の不履行であ り、法の要求する方法書作成義務違反であるというべきであ る。
アセス手続は、方法書をアセス調査のいわば、設計図とし て、出発点とするものである。手続の基本が違法であり存在 しないものであれば、これを基本として、その後に行われる 手続は、当然に違法となるというべきである。
9 本件方法書には記載がなく、追加・修正資料によってはじ めて明らかにした事実は次の通りである。
① 約1700万立方メートルの埋立土砂を沖縄県内外から調達すること(追加・修正資料41~42頁)
② 米軍がジェット機(C-35)を配置すること(同2頁)
③ 米軍航空機が集落上空を飛行することもあり得ること(同6頁)
④ 920mと430mの進入灯を設置すること(同3頁)
⑤ 洗機場を3か所設置すること(同4頁)
追加・修正資料の提出をせざるを得なかったのは、結局、公告・縦覧に供され、住民等の意見の対象となった本件方法書が環境影響評価方法書の体をなしておらず、環境影響評価方法書として必要な事項の記載が欠落していることを示すものである。
10 なお、県条例の方法書記載要件からいうと、前述のとお り、「対象事業計画の背景、検討経緯及び必要性」(改正前 は、「対象事業計画の検討経緯」)の記載が必要であるが、 その記載は追加・修正資料や準備書にも含まれていない。
a 沖縄県民の総意を無視しても、本件事業が必要であるとの 説明を、怠っているのである。
1997年12月21日には、「名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票」が実施され、投票の総数の54%余りが基地建設に反対の意思表示をした。
基地建設に反対する住民意思は明らかであって、これを尊重するのが、民主主義の基本である。
1996年7月16日、沖縄県議会は、「普天間飛行場の全面返還を促進し、基地機能強化につながる県内移設に反対する決議」を、全会一致で決議した。
本件基地建設の地元、名護、沖縄県のいずれも、本件基地建設に反対しているのであり、地方自治、住民意思を否定してでも本件基地建設を必要とする、事業の目的、及び内容を明示しなければならない。
本件方法書には、県民の総意に反しても実行すべき必要性を根拠づける、事業の目的及び内容を明示しなければならないが、事業の必要性に関する説明は、何らなされていない。
b 本事業予定地を選択した理由について、環境面からの説明 を怠っていること。
辺野古崎沿岸海域が、生物多様性豊かな地域であり、絶滅の危険性が最も高い絶滅危惧類等が生息する。
本件方法書には、このような生物多様性豊かな辺野古崎及びその沿岸海域に、なに故に、本事業が計画されたのか、環境面からの説明が、一切ないのである。
11 後出しされた、2度にわたる追加・修正資料の提出は、 環境影響評価法の定める手続を脱法するものである。
本来、環境影響評価方法書に記載すべき事項であって、 容易に記載しうる事項である。
環境影響評価法は、調査予測評価の手法が決定されてい ないとき場合には、対象事業に係る環境影響評価の項目を 記載するように求めているが、本件方法書で記載されなか った事項は、明らかに、批判を回避するための「意図的な 必要な記載要件の逸脱」といわざるを得ない。
そもそも、本来方法書に記載すべき事項を意図的に逸脱 し、環境影響評価法に定める手続(住民等意見、市町村意 見、県知事意見)のいずれの検討評価も受けることなく、
重要な事項に関して、追加変更した修正資料を提出したと しても、これは、本来、環境影響評価法の予定する手続と は異なり、脱法行為というべきであるから、事後に提出さ れた事項をもって、アセスの方法の決定があったとは言え ないのである。 追加修正事項は、環境影響評価方法書の 内容にはなり得ないというべきである。
12 端的に言えば、追加・修正資料、追加・修正資料(修正 版)は、環境影響評価法第5条の求める、方法書作成義務 に反する行為であり、前記の通りの手続を開始している事 情からしても、瑕疵を修補正する効果は生じない。
従って、本件環境影響評価方法書は、そもそも、作成義 務を尽くしておらず、違法であるというべきである。
13 いわばアセスの設計図である方法書が違法であるので あるから、その後の環境影響調査も方法書に基づかない、 違法な調査であり、その成果としても準備書も、いずれも 違法であり、それ以上に、極めて違法性が高いというべき である。
第4 環境影響評価方法書と、追加・修正資料、追加・修正資料 (修正版)の提出に対して、意見陳述の機会が与えられなかっ たこととその評価について
1 意見陳述権をどのように評価するかの問題である。
環境影響評価法第8条、第18条は、方法書及び準備書に対し、意見を 述べることを認めている。
これは、環境権ないしは環境に直接間接にかかわる住民の権利ないしは 利益を保護するために、法が手続的な権利ないしは法的保護に値する利益 を認め、これを保障するものというべきである。
良好な環境の保全は、持続可能な社会のために不可欠であ り人間生存の基礎であることから基本的人権であるといいう ると同時に、個人の主観的権利の保護だけでは保全しえない ものである。
その中から、環境保全の仕組みが構築され、国による環境 保護義務や、公共信託論が議論されている。
我が国の環境基本法の理念には、環境権や環境保護義務な どについての明確な法規や公共信託理論の立法化もなされて ないが、環境基本法3条は、環境の保全が「現在及び将来の 世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するととも に人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持される ように適切に行わなければならない」と規定している。これ は、国や個人の責務を認めたものということができ、基本法 の一つたる環境基本法のかような定めは、環境影響評価法 解釈においても、十分尊重されなければならない。
2 日本の環境法制は、世界的レベルに至っていない点もおおい。
ところで、オーフス条約は、環境問題に関する
(1)情報へのアクセス権、
(2)意思決定における市民参画、
(3)司法アクセス権についての国際的な最低基準
を定めたものである。
環境環法を解釈するには、世界的レベルを反映させながら
解釈すべきである。環境保護の世界性からしても、当然であ る。
3 すなわち、環境保護と、その享受を得るため、
ア 情報へのアクセス
イ 政策決定への参加
ウ 司法へのアクセス
を求めているのである。
4 わが国はオーフス条約に未加盟であるが、これをヨーロッ パ独自の法制度と無視するのは不当である。国際的な環境保 全のための法思想の展開、地球サミットのリオ宣言などを経 て、オーフス条約が今日の環境法の一つの到達点となっている ことを、わが国においても十分認識し、その思想を反映させて いく必要があるといわねばならない。
5 環境影響評価法における意見陳述の意義
① 環境影響評価手続の本質
さて、環境影響評価手続を、事業者に任せたままではどこまで環境配慮がされるかはわからないため、環境影響が大きいと予想される行為の選択については、これを社会的に管理することが必要となる。
アセスメントは環境を配慮した意思決定のための、社会的な手続きである。
環境問題は、選択を誤れば深刻かつ広範な被害をもたらすことになるが、その被害は第一次的に直接被害を受けると予想される者のみならず、環境の相互依存性から、全地球的な市民の利害に直接関わる事象である。
これに対して、事業実施主体が自ら環境配慮を行うだけでは、不十分な結果を招きかねず、そのために利害関係のある全市民に関与させて社会的決定をなそうとするのが環境影響評価手続の本質ということができる。
② 環境影響評価法の定め
ア わが国の環境影響評価法における環境影響評価手続は、 事業者が各段階の手順を進める度に住民と地方自治体にそ の成果を明らかにし、それらの意見を踏まえて環境影響評 価の内容を修正し、さらに必要に応じて前段階の手続まで 立ち戻って手続をやり直すことによって、適切な環境影響 評価がなされるべく予定している。
すなわち、事業者は、方法書作成後には、住民意見(同法8条 以下引用法律同じ)と都道府県知事等の意見(10条)を受け、前者の意見に「配意し」、後者の意見を「勘案」して方法書の事項に検討を加え、「対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。」(11条1項)。そして、環境影響評価を実施(12条)した後に作成する準備書についても、住民意見(18条)と都道府県知事等の意見(20条)を受け、準備書を修正して評価書を作成することになる(21条)。
その結果、「対象事業の目的及び内容」に修正を加える場合には原則として方法書作成からやり直しを求められる(21条1項1号 5条1項2号)。また、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法、環境影響評価の結果や環境保全措置等に修正がある場合にはその部分についてさらに環境影響評価を行わなければならない(21条1項3号)。
また、方法書の公告後に対象事業の目的及び内容に修正が生じた場合には、修正後の事業について改めて環境影響評価手続を行わなければならず(28条)、評価書の公告後の情況の変化等により環境影響評価の変更の必要が生じた場合にはそれについて環境影響評価を行う手続も規定されている(32条)。
このように、環境影響評価手続においては、環境影響評価の項目や手法の選定、その実施の結果に対する評価等について、対象事業の目的と内容を明らかにして関連づけ、住民や都道府県知事等の意見を幾層もの段階で反映させることによって、その適正が担保される仕組みになっている。
イ 環境影響評価法が、方法書、準備書及び評価書の多数の段階における公告縦覧を求め、住民や地方自治体等からの意見を求める仕組みとされているのは、前述のとおり、今日における環境保全が、単に事業者の自主的な努力のみによってはなされえず、地域住民の参加を経て社会的合意を図ることによってなされるべきであるという発想に立っていることからである。
③ 環境影響評価における市民参加
環境の保全は、環境破壊によって一次的直接的に権利を侵害 される当事者のみならず、全市民、そして将来世代にわたっ ての持続可能な発展のために不可欠のものと認識されてきて おいる。
環境影響評価手続における市民参加は、全市民に対し、環 境保全のための権利を付与し責務を課すことによって、実効 性を図ろうとするものである。
したがって、環境影響評価法の制定によって、同法に定めた住民参加の上記諸規定は、住民に対して、それら手続的権利の保障を明らかにしたものということができるのである。

Posted by しゅんさん at 21:45│Comments(0)