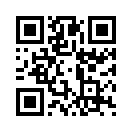› しゅんさんブログ › 辺野古環境影響評価書 3
› しゅんさんブログ › 辺野古環境影響評価書 32011年12月20日
辺野古環境影響評価書 3
国は、それでもなお、辺野古環境影響評価書を提出しようとしています。
オスプレイは、離着陸時にその着地地面を200度にも上昇させるそうです。
北九州空港設置のための埋め立てに際しては、空港を使用する航空機ごとに騒音のシュミレーションを行わせています、辺野古では、航空路はおろか使用航空機も隠蔽したまま、アセスを強行しよとしています。
嘘の上に嘘を重ねる「環境影響調査」 最初からやり直す以外にはないのです。
意見 その 3 です。
第5 環境影響評価方法書提出から、準備書提出の間に、事業内 容の追加がなされたこと。
本件準備書には、「追加・修正資料(修正版)」にも記載さ れていなかった施設が事業内容に追加されていた。
ア ヘリパッドが4か所設置されること(本件準備書2-6、 2-8頁)
イ 係船機能付きの護岸が設置されること(同2-6、2- 8~9)
ウ 汚水処理浄化槽が設置されること(同2-6、2-8)
これら本件準備書において追加された施設については、方法 書手続きにおいて全く検討がなされていないにもかかわらず、 環境影響評価だけが行われたのである。
従って、これらの事項は、環境影響評価法の求める環境影響 評価方法書作成に伴う、一連の手続を逸脱する、違法な手続で あって、そもそも、準備書作成義務の前提としての方法書作成 義務を履行していないのであって、違法であると言うべきであ る。
第6 アセス準備書提出後の自主環境調査
1 環境影響評価法の認める事後調査とは異なる。
沖縄防衛局による調査継続は、本件準備書作成のために複数年調査を行っていないなど、環境影響調査が不十分であることを自ら認めているようなものである。
沖縄防衛局は、本件準備書作成のための環境影響調査が不十分であると指摘されることを見越して、後に作成される予定の環境影響調査評価書に掲載する目的で調査を継続しているとしか考えられない。
沖縄防衛局は、「準備書縦覧後に実施している現況調査は、事後調査や環境監視調査をより効率的・効果的に実施するため、環境上特に重要と考えられる項目について、データを蓄積する目的で、自主的に実施しているものであり、環境影響評価手続上のものではありません。」などと説明しているが、工事に着工する以前の時期における調査は、方法書にその手法が記載され、準備書作成のための環境影響調査としてなされるべきである。
「事後調査や環境監視調査をより効率的・効果的に実施するため、環境上特に重要と考えられる項目について、データを蓄積する目的」との目的では全く説明がつかない。まさに、準備書作成のための環境影響調査としてなされるべき調査である。
また、このような調査に関しては、住民らは、その内容について、意見を述べる機会を奪われることになる。
手続的にも、環境影響評価法の要求する手続を逸脱するものであって、違法であるというべきである。
第7 法の手戻り要件
1 本来、5条、14条 方法書、準備書 作成義務違反
2 環境影響評価法28条は、方法書公告後、評価書公告までの 間に、事業内容の修正があった場合は、例外的に軽微な場合を 除き、原則として環境影響評価手続を方法書作成から再度実施 しなければならないものと定めている。
環境影響評価法施行令(以下「施行令」という。)12条が引用する同9条は、法28条が定める例外に該当する「軽微な修正」の中身を明らかにしている。
施行令9条は、具体的な数値をもって一定規模以下の変更は「軽微な修正」に該当するとしながら、
「環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く」としている。
要するに、施行令9条に定める一定規模以下の変更に該当する場合は、例外的に、方法書作成からの再実施は不要であるが、一定規模以下の変更であっても、「環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情」がある場合には、原則に戻り、方法書手続からの再実施が必要になる。
原則と例外を取り違えるべきではない。
3 軽微な変更か。
① 埋め立てに関して。
環境影響評価法第28条は、
7条の規定による公告(方法書)を行ってから、27条の規定による公告(評価書)まで、5条1項2号に該当する事項を修正使用とする場合、修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正の事業について第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。
但し、当該事項の修正事項が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正、その他の政令で定める修正については、この限りではない。原則やり直しであり、例外的にやり直し不要となる。
9条でいう、政令で定める軽微な変更とは、施工令3条に定めがあり、
別表3により埋め立てで、軽微な変更となるのは、
ア 新たな埋め立て干拓地域の面積が、
変更前の面積の10%未満
イ 対象区域から、500メートル以上 離れた区域が対象とならないこと
の変更が軽微な修正の前提となっている。
② 空港に関しては、県条例が適用される。
条例25条では、施行令別表に従うことになっており、 飛行場建設で、軽微といえるのは、
① 滑走路の長さ
滑走路の長さが20%以上増加しないこ と。
② 飛行場及びヘリポートの区域の位置
新たな飛行場およびヘリポート区域とな る部分の面積が10ヘクタール未満(特 別配慮地域における対象事業にあっては、 7ヘクタール未満)であること。
の変更が軽微な変更と扱われることになっている。
ところで、県は、「普天間代替施設で滑走路部分は県アセス条例の対象。県条例では、アセスをやり直さずに修正可能な「軽微な変更」の範囲について「飛行場区域面積が10ヘクタール未満」と定めている。
県はその移動幅を代替施設の長さ1800メートルから 「56メートル未満」と算出。手続きの中で3回予定される 知事意見のたびに、55メートルまで移動が可能」とみてい る。(琉球新報 2007年11月2日)
また、2009年4月18日の県の見解でも、
「アセス条例の規則では、アセスをやり直さずに可能な飛行場部分の軽微な修正範囲は10ヘクタール以内。1800メートルの滑走路幅では移動幅は約55メートルとなる。県側は、アセス条例の規則を根拠に(1)事業主による自主的移動(2)知事意見への対応措置としての軽微な修正(3)環境への負荷の低減を目的とする修正-で沖合移動が可能だとの見解」のようである。
要するに、飛行場(滑走路)を移動させても、アセス手続のやり直しをしないで可能であるとの見解のようである。
③ しかし、この見解は明らかに誤りである。
県条例にしたがって、飛行場位置を変更しながら、アセス手続のやり直しを回避することはできないというべきである。
まず、環境影響評価法施行令「別表第二(第9条関係)」及び「別表第三(第13条関係)では、
国アセス対象飛行場の変更に関して、軽微な変更の範囲を
① 滑走路の長さ 300メートルを超えて増加しないこ と。
② 飛行場及びその施設の区域の位置
新たに飛行場及びその施設の区域とな る部分の面積が20ヘクタール未満で あること。
③ 対象事業区域の位置
変更前の対象事業区域から500メー トル以上離れた区域が新たな事業区域 とならないこと。
④ 利用を予定する航空機の種類または数
変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行 場周辺における航空機騒音による障害 の防止等に関する法律施行令第6条の 規定を適用した場合における同条の値 が75以上となる区域)から500メ ートル以上離れた陸地の区域が新たに 当該区域にならないこと。
が、軽微な事項に当たるとしている。
これに対して、沖縄県環境影響評価条例施行規則は、環境影響評価法の別表のうち、① ②のみが軽微な変更の対象としているのであり、位置の変更や、利用航空機の種類、数については、これを軽微な変更として、アセス手続のやり直しを免れる根拠とは規定されていないのである。
アセス手続は、原則やり直しであり、軽微な場合には、やり直しを免れるという、規定であり、県条例は、滑走路の移動が有ったとき、これを再アセスの対象外とする規定はないのである。また、利用予定飛行機に関してもオスプレイの利用が確実であれば、当然にこれを前提としないアセス手続は
やり直し必要を生じることになる。
軽微な事項は法定要件の有る場合に限り、滑走路位置の移動は、除外事項として法定されていないのであるから、全て、やり直しの対象となる。
環境影響評価法の空港に関する事項と比較すると、県条例は移動を例外とせず、手続のやり直しを求めているのであって、政令で、軽微な事項に当たらないとされるもの以外は、
対象となるというべきである。
(2) 本件で、やり直しが必要である事項は次ぎの通りである。
① 約1700万立方メートルの埋立土砂を沖縄県内外から調達すること(追加・修正資料41~42頁)
② 米軍がジェット機(C-35)を配置すること(同2頁)
③ 米軍航空機が集落上空を飛行することもあり得ること(同6頁)
④ 920mと430mの進入灯を設置すること(同3頁)
⑤ 洗機場を3か所設置すること(同4頁)
⑥ ヘリパッドを4か所設置すること(本件準備書2-6、2-8 頁)
⑦ 係船機能付きの護岸を設置すること(同2-6、2-8~9頁)
⑧ 汚水処理浄化槽を設置すること(同2-6、2-8頁)
これらは、いずれも、環境に重大な影響を与えることを当然に予測させるものであり、前記の特別の事情に該当することは明らかである。
よって、沖縄防衛局は、上記事項を全て含めて、再度、方法書の作成から手続をやり直さなければならない。
第8 準備書の作成のやり直し
1 これまで述べたように、環境影響評価法14条により、準備 書作成義務を事業者に認めている。
方法書作成も回避し、違法な手法によってなされた環境影響 調査に基づく方法書は、違法であって、作成義務そのものを尽 くしているとはいえない。
2 作成しなおすのは当然である。
但し、直ちに新たな手続を行うことは不相当である。
違法な環境影響調査によって、環境は既に破壊されており、
その回復に要する期間を経過した後に、しかも、ゼロオプショ ンを選択肢とした上で、方法書から、手続をやり直すべきであ る。
なお、他府県ではその大半で、公聴会制度をつくっている。
沖縄においても公聴会制度を導入して、公開された議論の場を保 障すべきである、


オスプレイは、離着陸時にその着地地面を200度にも上昇させるそうです。
北九州空港設置のための埋め立てに際しては、空港を使用する航空機ごとに騒音のシュミレーションを行わせています、辺野古では、航空路はおろか使用航空機も隠蔽したまま、アセスを強行しよとしています。
嘘の上に嘘を重ねる「環境影響調査」 最初からやり直す以外にはないのです。
意見 その 3 です。
第5 環境影響評価方法書提出から、準備書提出の間に、事業内 容の追加がなされたこと。
本件準備書には、「追加・修正資料(修正版)」にも記載さ れていなかった施設が事業内容に追加されていた。
ア ヘリパッドが4か所設置されること(本件準備書2-6、 2-8頁)
イ 係船機能付きの護岸が設置されること(同2-6、2- 8~9)
ウ 汚水処理浄化槽が設置されること(同2-6、2-8)
これら本件準備書において追加された施設については、方法 書手続きにおいて全く検討がなされていないにもかかわらず、 環境影響評価だけが行われたのである。
従って、これらの事項は、環境影響評価法の求める環境影響 評価方法書作成に伴う、一連の手続を逸脱する、違法な手続で あって、そもそも、準備書作成義務の前提としての方法書作成 義務を履行していないのであって、違法であると言うべきであ る。
第6 アセス準備書提出後の自主環境調査
1 環境影響評価法の認める事後調査とは異なる。
沖縄防衛局による調査継続は、本件準備書作成のために複数年調査を行っていないなど、環境影響調査が不十分であることを自ら認めているようなものである。
沖縄防衛局は、本件準備書作成のための環境影響調査が不十分であると指摘されることを見越して、後に作成される予定の環境影響調査評価書に掲載する目的で調査を継続しているとしか考えられない。
沖縄防衛局は、「準備書縦覧後に実施している現況調査は、事後調査や環境監視調査をより効率的・効果的に実施するため、環境上特に重要と考えられる項目について、データを蓄積する目的で、自主的に実施しているものであり、環境影響評価手続上のものではありません。」などと説明しているが、工事に着工する以前の時期における調査は、方法書にその手法が記載され、準備書作成のための環境影響調査としてなされるべきである。
「事後調査や環境監視調査をより効率的・効果的に実施するため、環境上特に重要と考えられる項目について、データを蓄積する目的」との目的では全く説明がつかない。まさに、準備書作成のための環境影響調査としてなされるべき調査である。
また、このような調査に関しては、住民らは、その内容について、意見を述べる機会を奪われることになる。
手続的にも、環境影響評価法の要求する手続を逸脱するものであって、違法であるというべきである。
第7 法の手戻り要件
1 本来、5条、14条 方法書、準備書 作成義務違反
2 環境影響評価法28条は、方法書公告後、評価書公告までの 間に、事業内容の修正があった場合は、例外的に軽微な場合を 除き、原則として環境影響評価手続を方法書作成から再度実施 しなければならないものと定めている。
環境影響評価法施行令(以下「施行令」という。)12条が引用する同9条は、法28条が定める例外に該当する「軽微な修正」の中身を明らかにしている。
施行令9条は、具体的な数値をもって一定規模以下の変更は「軽微な修正」に該当するとしながら、
「環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く」としている。
要するに、施行令9条に定める一定規模以下の変更に該当する場合は、例外的に、方法書作成からの再実施は不要であるが、一定規模以下の変更であっても、「環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情」がある場合には、原則に戻り、方法書手続からの再実施が必要になる。
原則と例外を取り違えるべきではない。
3 軽微な変更か。
① 埋め立てに関して。
環境影響評価法第28条は、
7条の規定による公告(方法書)を行ってから、27条の規定による公告(評価書)まで、5条1項2号に該当する事項を修正使用とする場合、修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正の事業について第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。
但し、当該事項の修正事項が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正、その他の政令で定める修正については、この限りではない。原則やり直しであり、例外的にやり直し不要となる。
9条でいう、政令で定める軽微な変更とは、施工令3条に定めがあり、
別表3により埋め立てで、軽微な変更となるのは、
ア 新たな埋め立て干拓地域の面積が、
変更前の面積の10%未満
イ 対象区域から、500メートル以上 離れた区域が対象とならないこと
の変更が軽微な修正の前提となっている。
② 空港に関しては、県条例が適用される。
条例25条では、施行令別表に従うことになっており、 飛行場建設で、軽微といえるのは、
① 滑走路の長さ
滑走路の長さが20%以上増加しないこ と。
② 飛行場及びヘリポートの区域の位置
新たな飛行場およびヘリポート区域とな る部分の面積が10ヘクタール未満(特 別配慮地域における対象事業にあっては、 7ヘクタール未満)であること。
の変更が軽微な変更と扱われることになっている。
ところで、県は、「普天間代替施設で滑走路部分は県アセス条例の対象。県条例では、アセスをやり直さずに修正可能な「軽微な変更」の範囲について「飛行場区域面積が10ヘクタール未満」と定めている。
県はその移動幅を代替施設の長さ1800メートルから 「56メートル未満」と算出。手続きの中で3回予定される 知事意見のたびに、55メートルまで移動が可能」とみてい る。(琉球新報 2007年11月2日)
また、2009年4月18日の県の見解でも、
「アセス条例の規則では、アセスをやり直さずに可能な飛行場部分の軽微な修正範囲は10ヘクタール以内。1800メートルの滑走路幅では移動幅は約55メートルとなる。県側は、アセス条例の規則を根拠に(1)事業主による自主的移動(2)知事意見への対応措置としての軽微な修正(3)環境への負荷の低減を目的とする修正-で沖合移動が可能だとの見解」のようである。
要するに、飛行場(滑走路)を移動させても、アセス手続のやり直しをしないで可能であるとの見解のようである。
③ しかし、この見解は明らかに誤りである。
県条例にしたがって、飛行場位置を変更しながら、アセス手続のやり直しを回避することはできないというべきである。
まず、環境影響評価法施行令「別表第二(第9条関係)」及び「別表第三(第13条関係)では、
国アセス対象飛行場の変更に関して、軽微な変更の範囲を
① 滑走路の長さ 300メートルを超えて増加しないこ と。
② 飛行場及びその施設の区域の位置
新たに飛行場及びその施設の区域とな る部分の面積が20ヘクタール未満で あること。
③ 対象事業区域の位置
変更前の対象事業区域から500メー トル以上離れた区域が新たな事業区域 とならないこと。
④ 利用を予定する航空機の種類または数
変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行 場周辺における航空機騒音による障害 の防止等に関する法律施行令第6条の 規定を適用した場合における同条の値 が75以上となる区域)から500メ ートル以上離れた陸地の区域が新たに 当該区域にならないこと。
が、軽微な事項に当たるとしている。
これに対して、沖縄県環境影響評価条例施行規則は、環境影響評価法の別表のうち、① ②のみが軽微な変更の対象としているのであり、位置の変更や、利用航空機の種類、数については、これを軽微な変更として、アセス手続のやり直しを免れる根拠とは規定されていないのである。
アセス手続は、原則やり直しであり、軽微な場合には、やり直しを免れるという、規定であり、県条例は、滑走路の移動が有ったとき、これを再アセスの対象外とする規定はないのである。また、利用予定飛行機に関してもオスプレイの利用が確実であれば、当然にこれを前提としないアセス手続は
やり直し必要を生じることになる。
軽微な事項は法定要件の有る場合に限り、滑走路位置の移動は、除外事項として法定されていないのであるから、全て、やり直しの対象となる。
環境影響評価法の空港に関する事項と比較すると、県条例は移動を例外とせず、手続のやり直しを求めているのであって、政令で、軽微な事項に当たらないとされるもの以外は、
対象となるというべきである。
(2) 本件で、やり直しが必要である事項は次ぎの通りである。
① 約1700万立方メートルの埋立土砂を沖縄県内外から調達すること(追加・修正資料41~42頁)
② 米軍がジェット機(C-35)を配置すること(同2頁)
③ 米軍航空機が集落上空を飛行することもあり得ること(同6頁)
④ 920mと430mの進入灯を設置すること(同3頁)
⑤ 洗機場を3か所設置すること(同4頁)
⑥ ヘリパッドを4か所設置すること(本件準備書2-6、2-8 頁)
⑦ 係船機能付きの護岸を設置すること(同2-6、2-8~9頁)
⑧ 汚水処理浄化槽を設置すること(同2-6、2-8頁)
これらは、いずれも、環境に重大な影響を与えることを当然に予測させるものであり、前記の特別の事情に該当することは明らかである。
よって、沖縄防衛局は、上記事項を全て含めて、再度、方法書の作成から手続をやり直さなければならない。
第8 準備書の作成のやり直し
1 これまで述べたように、環境影響評価法14条により、準備 書作成義務を事業者に認めている。
方法書作成も回避し、違法な手法によってなされた環境影響 調査に基づく方法書は、違法であって、作成義務そのものを尽 くしているとはいえない。
2 作成しなおすのは当然である。
但し、直ちに新たな手続を行うことは不相当である。
違法な環境影響調査によって、環境は既に破壊されており、
その回復に要する期間を経過した後に、しかも、ゼロオプショ ンを選択肢とした上で、方法書から、手続をやり直すべきであ る。
なお、他府県ではその大半で、公聴会制度をつくっている。
沖縄においても公聴会制度を導入して、公開された議論の場を保 障すべきである、
Posted by しゅんさん at 21:17│Comments(0)